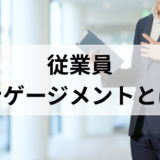1.「公益通報者保護制度」とは?
「ウチの会社で違法行為が!?」。リコールに相当する不良品が出荷されているのにリコールを行わない、当局への報告が義務付けられているレベルの重大事故が起きたにもかかわらず報告を行わない、あるいは取り扱う産品の産地を偽ってブランド力の高い産品に見せかける、そのようなリコール隠しや事故の隠蔽、産地偽装などの不祥事が起きています。
そうした不祥事が明るみに出たきっかけの多くは、その企業や取引先企業などで働く人から行政機関、報道機関などへの通報でした。
こうした、企業をはじめとする事業者による一定の違法行為などを、労働者が組織内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といいます。公益通報は、組織の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになりますが、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあります。
そこで、不正の目的でなく通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産などを保護するために「公益通報者保護法」が平成16年(2004年)に成立・公布され、平成18年(2006年)4月1日に施行されました。
しかし、同法の施行後も、事業者が公益通報に適切に対応しない事案や公益通報者の保護が十分に図られていない事案が生じたことから、事業者における公益通報への適切な対応を確保し、公益通報者の保護が図られるよう、改正がなされました。この改正法が令和4年(2022年)6月1日に施行されました。
では、どのような通報が「公益通報」に当たり、通報した人がどのように守られるのかなどをご紹介します。
2.どんな通報が「公益通報」になるの?
公益通報者保護法では、「誰が」「どのような事実について」「どこに通報するか」など、一定の要件を満たすものが公益通報とされ保護の対象になります。具体的には次の要件になります。
(1)通報者は「労働者など」であること
公益通報者保護法によって保護される通報者は、企業などの「労働者など」であることが求められます。
「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイトなども含まれます。
令和4年(2022年)6月1日以降は、「退職者」、つまり現に勤務先で働いている労働者だけではなく、勤務先を退職してから1年以内の退職者や、派遣先での勤務終了から1年以内の退職者も含まれます。
さらに、「役員」も含まれます。
(2)通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為などであること(通報対象事実)
通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為であることが求められます。
対象ではない法律に違反しても、その通報者は公益通報者保護法による保護の対象になりません。
「通報対象事実」とは ~公益通報の対象になる事実とは
※対象となる法律の例:刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、
大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他
「通報対象事実」の例
・「犯罪行為」の例
- 他人のものを盗んだり、横領したりする
- 安全基準を超える有害物質が含まれる食品を販売する
- 無許可で産業廃棄物の処分をする
- リコールに相当する不良車が発生したにも関わらず、虚偽の届出をする(届出義務違反(※))
- リコールの勧告を受けたが改善措置を講じない(勧告違反(※))
- 改善の命令を受けたが改善措置を講じない(命令違反(※))
・「過料対象行為」の例
- 道路運送車両法で規制されている自動車会社が無資格者による完成検査を行うこと
- 金融商品販売業者が勧誘方針を定めないこと
(3)通報先
通報先には次の3つが定められています。この3つには優先順序があるわけではなく、自分の通報したい先に通報することができます。なお、保護されるための要件(※)がそれぞれに定められています。
・事業者内部
公益通報者保護法に基づき、事業者は、組織内部で内部通報を受け付ける窓口を設置することが義務付けられています。通報先の例としては、そのような事業者内の内部通報窓口や、事業者が契約する外部の法律事務所・通報専門業者などがあります。また、管理職や上司も通報先となる場合があります。
・行政機関
通報された事実について、勧告、命令の権限を有する行政機関が通報先になります。一般には、通報対象事実に関連する行政機関と考えてもよいでしょう。
もし通報しようとした行政機関が適切でなかった場合、その行政機関は適切な通報先を通報者に紹介する義務があります。
・報道機関など
報道機関や消費者団体、労働組合など、そこへの通報が被害の発生や拡大を予防するために必要であると認められるものが通報先になります。
※通報先ごとの保護要件について詳しくはこちら
「公益通報者保護制度~通報者の方へ」
公益通報は、組織の違法行為などの是正を期待して行われるものです。そのため、通報を受けた民間事業者や行政機関などは、必要がある場合は適切な是正措置をとったり、是正措置などについて公益通報者に知らせたりする必要があります。
3.通報者は、どのように保護されるの?
公益通報を理由とした解雇は無効となり、降格、減給、退職の強要などの不利益な取扱いは禁止されています。
また、事業者は、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務を負います。
さらに、事業者は、通報者の保護のため、通報窓口の担当者や案件の調査を行う担当者のうち、通報者の氏名などが分かる情報を知る立場にある者を「従事者」として指定する義務を負います。「従事者」は、公益通報者保護法が定める守秘義務を負い、万一この義務に違反した場合は、従事者に罰金30万円が科せられることになります。このような刑事罰によっても、通報者の秘密は保護されています。
民間事業者がこれらの義務に違反した場合、消費者庁から報告を求められたり、助言、指導、もしくは勧告を受けることがあります。民間事業者が勧告にも従わない場合、公表されることもあります。
公益通報者の保護の内容
(1)勤務先(労働契約・委任契約を結んでいる事業者)からの保護
・解雇の無効
公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者(公益通報者を使用する事業者)が公益通報者に対して行った解雇は無効です。
ただし、公益通報者が役員の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者を解任することは可能ですが、公益通報者は、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。
・不利益な取扱いの禁止
公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることも禁止されています。具体的には、次のような取扱いが禁止されます。
さらに、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません。
不利益な取扱いの例
| 降格 | 給与上の差別 |
| 減給 | 退職の強要 |
| 訓告 | もっぱら雑事に従事させる |
| 自宅待機命令 | 退職金の減額・没収 |
(2)派遣先からの保護
※通報者が派遣労働者の場合
事業者は、派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣先が行った労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めることなど、公益通報者に対し不利益な取扱いをすることも禁止されています。
*公務員についても、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されています。
4.事業者にはどんな意義があるの?
公益通報者保護法は、規模や営利、非営利を問わず全ての事業者に適用されるものです。そして、その組織内で常時働いている労働者の数が301名以上の事業者は、この法律に基づく体制(「内部公益通報対応体制」といいます。)の仕組みを整備するとともに、これを適切に運用することが求められます。
内部公益通報対応体制とは、組織内の従業員などから通報を受け付け、通報者の保護を図りながら、適切な調査や是正、再発防止策などを行う事業者内の仕組みをいいます。具体的には、通報窓口を設置したり、内部規程を整備・運用したりすることなどです。
事業者が内部通報制度を整備し、通報者を保護することには、事業者自身が違法行為を早期に把握し、自浄作用を発揮させることにより違法行為の是正を図ることが可能となるという意義もあります。
事業者が実効性のある内部公益通報対応体制を整備・運用することは、法令遵守の推進や組織の自浄作用の向上に寄与し、ステークホルダーや国民からの信頼の獲得にも資するものです。また、内部公益通報制度を積極的に活用したリスク管理などを通じて、事業者が適切に事業を運営し、商品・サービスを提供していくことは、事業者の社会的責任を果たすとともに、ひいては持続可能な社会の形成に寄与するものであります。
このような意義を踏まえ、事業者は、公正で透明性の高い組織文化を育み、組織の自浄作用を健全に発揮させるため、経営トップの責務として、法令などを踏まえた内部公益通報対応体制を構築するとともに、事業者の規模や業種・業態などの実情に応じて一層充実した内部公益通報対応体制の仕組みを整備・運用することが期待されます。
 ハコラボ
ハコラボ