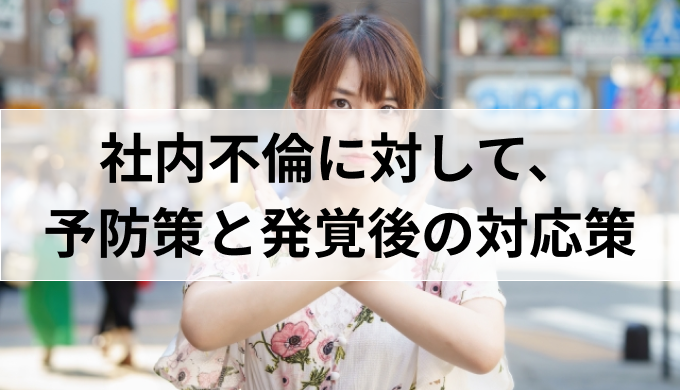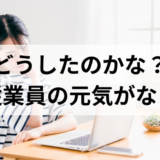どんな集団においても、男女がひとつの場所に集まれば、そこに恋愛が発生してしまうのは避けられない事態なのかもしれません。
しかし、人事担当としては、この「不倫問題」は、対岸の火事というわけにはいきません。会社は非常に濃密な人間関係の発生する場であり、「社内恋愛」や「社内不倫」は発生するものです。問題は、リスク回避をミッションとする企業の人事担当が「社内恋愛」や「社内不倫」に対してどこまで、どのように介入すべきかということです。そこで本稿では、人事担当としての「社内恋愛」や「社内不倫」への対応策について解説していきます。
「社内不倫」や「社内恋愛」が問題となるのはどういう時か
まず大前提として「社内恋愛」は、それ自体普通であれば人事がわざわざ当人たちに口を出すような事柄ではありません。なぜなら恋愛は個人の自由であって、それを会社が管理・制限することがあってはならないからです。
次に「社内不倫」についてはどうでしょうか?こちらも、基本的には大人同士のプライベートな恋愛事情によるものなので、人事から積極的に介入していくのは不自然です。ただし「不倫」は民法上の不法行為に当たるため、会社内の業務に持ち込まれると、トラブルの温床になりやすいのです。「社内恋愛」とは違い、場合によっては当事者たちの動向を注意深く見ていく必要があります。
そして「社内恋愛」「社内不倫」いずれの場合においても、会社に不利益が発生した場合は、話が違ってきます。以下のような場合は、見ているだけではなく、トラブルが大きくなる前に人事として積極的に何らかの対策を打たなければなりません。
ケース1:「社内不倫」「社内恋愛」によって不正行為が発生した時
恋愛感情のもつれから当人同士の関係が悪化すると、ちょっとした諍いがエスカレートして、立場の強い者から立場の弱い者にセクハラ・パワハラとみなされる行為に発展することがあります。また社内恋愛と業務で公私混同が発生し、当人たちが経費精算や勤怠データに不正を働くことがあります。
ケース2:「社内不倫」「社内恋愛」によって業務の生産性が低下した時
上記ケース1同様、破局した際のパフォーマンスの低下や、彼らがもたらすギスギスした関係性が、時には周りの同僚に業務に支障をきたすレベルで不快感を与える場合があります。また「社内不倫」の場合は、配偶者が社外からクレームを入れてくることもしばしばあります。これらは、すべて業務の生産性低下につながるトラブルであると言えます。
ケース3:「社内不倫」「社内恋愛」によって情報漏えい・機密保持にリスクが発生した時
恋愛関係にある一方の社員が、高度に情報の機密性を保持しなければならない部署で勤務している時、恋愛相手につい気を許し、部署外へ公開してはならない情報が漏れてしまうことがしばしばあります。
要するに、不倫関係や恋愛関係が当人同士のプライベートな範囲内で自己完結できず、会社の業務に不利益を与えたとみなされる場合、直属の上司や経営陣と連携しながら、人事としても何らかの手を打たなければならない、と考えてください。
「社内不倫」や「社内恋愛」が発覚した際、どうすれば良いのか?
社内での恋愛や不倫については、その当時者は大抵の場合、周りに波風を立てたくないため、積極的に二人の関係性を自分たちからひけらかすようにアピールするケースは多くはありません。
にもかかわらず「社内不倫」や「社内恋愛」について、その事実が当事者以外に知れ渡り、彼らと直接関係のない人事部の耳にも入るような状態になっているということは、彼らに近い部署の従業員たちは、その関係性をほぼ全員が知っているとみなしたほうがよいでしょう。いわば、脇が甘いわけです。したがって「社内恋愛」はともかく、社内で誰しもが公然の事実として知っている「社内不倫」については、基本的には何らかの問題が発生している可能性があると疑ってかかったほうがよいのです。
ですから、まずは人事部として問題のありそうな社内恋愛・社内不倫関係の情報を掴んだ時は、状況に応じて事実関係について彼らの周囲や上位職の従業員からヒアリングを行ったほうがよいかもしれません。そして調査した結果、会社への不法行為や生産性の低下が見られた場合は、具体的な対策を検討していくことになります。
人事が取り組むべき2つの対策
では、人事が取り組むべき対策とは一体どのようなものなのでしょうか?それは、大きく分けると2つあります。トラブルを未然に防ぐための「予防」対策と、実際に問題が起こってからの事後の「解決策」です。順番に詳細を見ていきます。
取り組み1:問題の予防
問題の「予防」と言っても、有名なアイドルグループのように「恋愛禁止」を就業規則に盛り込む、といった直接的な対策ではありません。厳密に言うと就業規則に「恋愛禁止」を明記すること自体は問題ありませんが、法律上無効なため、恋愛禁止条項を根拠に処分するのは不可能ですし、率先して社内恋愛や社内結婚を推奨している企業があるのも事実です。
また、恋愛禁止を押し付けると、社員の間に余計な反発や不満を発生させるだけとなります。会社という場は、人間同士の関係性が濃密になる場でもあるので、その中で自然に発生する恋愛感情を止めることはできないと考えたほうがよいでしょう。
ですから、この場合の「予防」とは、もし問題が起こった場合、人事として対策を打ちやすくするための事前準備をする、という意味になります。具体的には、以下の3点を実施していくとよいでしょう。
予防策1:就業規則の整備
大半の企業では恐らく問題ないかと思われますが、もし不安がある場合は、就業規則の罰則・懲戒系の項目に「公序良俗に違反した場合」「社内の風紀・秩序を乱す行為をした時」といった文言が入っているかどうか確認しましょう。これら項目は、社内不倫や社内恋愛において、会社に不利益が発生するような自体が発生した際に、懲戒処分を行う時の根拠として必要となります。
予防策2:社員教育の徹底
新入社員研修や管理職研修など、会社で実施している各階層別研修があれば、「社内恋愛」「社内不倫」について具体的なトラブル事例・懲戒事例なども交えつつ、会社の取り組みを説明する講義を盛り込みましょう。もし定期的な研修プログラムがなければ、臨時の社員研修を実施するのも有効です。
予防策3:社内通報制度(ホットライン)の整備
「社内恋愛」「社内不倫」では、関係性が一旦崩れると、社内で立場が強い方が弱い方に対してセクハラ行為やパワハラ行為を行うトラブルへと発展しやすいものです。また、社内恋愛や社内不倫が不正や周囲の労働環境を悪化させることもあります。その時のために、もしまだ未整備であれば、社内で不正・セクハラ・パワハラについてのホットラインを設置し、問題があれば人事をはじめ、第三者が公平な観点で調査・対応できるような仕組みを整備しておきましょう。
取り組み2:問題発覚後の対策
予防策を講じたとしても、やはり「社内恋愛」や「社内不倫」によるトラブルはどうしても発生するものです。当該社員による恋愛や不倫のもつれによって、会社に具体的な不利益が発生した場合は、強めの対策が必要です。基本的に「厳重注意」や「転勤」など、懲戒的なニュアンスを含んだ処分を課して再発防止を図る必要があります。基本的にはケースバイケースの対応となりますが、ここでは2つだけ守るべき原則を書いておきます。
原則1:社内の立場が強いほうに対して異動を伴う処分を行う
もし、具体的な対応に踏み込む際は、必ず社内での立場が強いほうの社員に対して、配置転換を前提とした懲戒処分・人事異動を行うよう調整しましょう。立場が強いほうの社員を「物理的に」離してしまえば自然に関係が終わることも多く、それに伴うトラブルが解決することもあります。
原則2:処分は迅速に・内密に
配置転換を伴う懲戒処分などを行った際は、関係者と人事部、経営陣以外に社内不倫、社内恋愛やそのトラブルなどの事実を公開するのは控えましょう。配置転換をする場合は、社内外向けにわかりやすい理由を公表し、できるだけ早期に対応するようにしましょう。処分までの意思決定が長引くと、新たなトラブルが発生しかねないからです。
最後に
「社内恋愛」「社内不倫」は非常にデリケートな問題であり、かつ、1件1件非常に細やかな対応が求められます。だからこそ、しっかりと人事としての対応方法や基準を予め決めておいて、いざ問題が起こった時はきちんと組織として対応できるようにしておくことが大切です。
 ハコラボ
ハコラボ